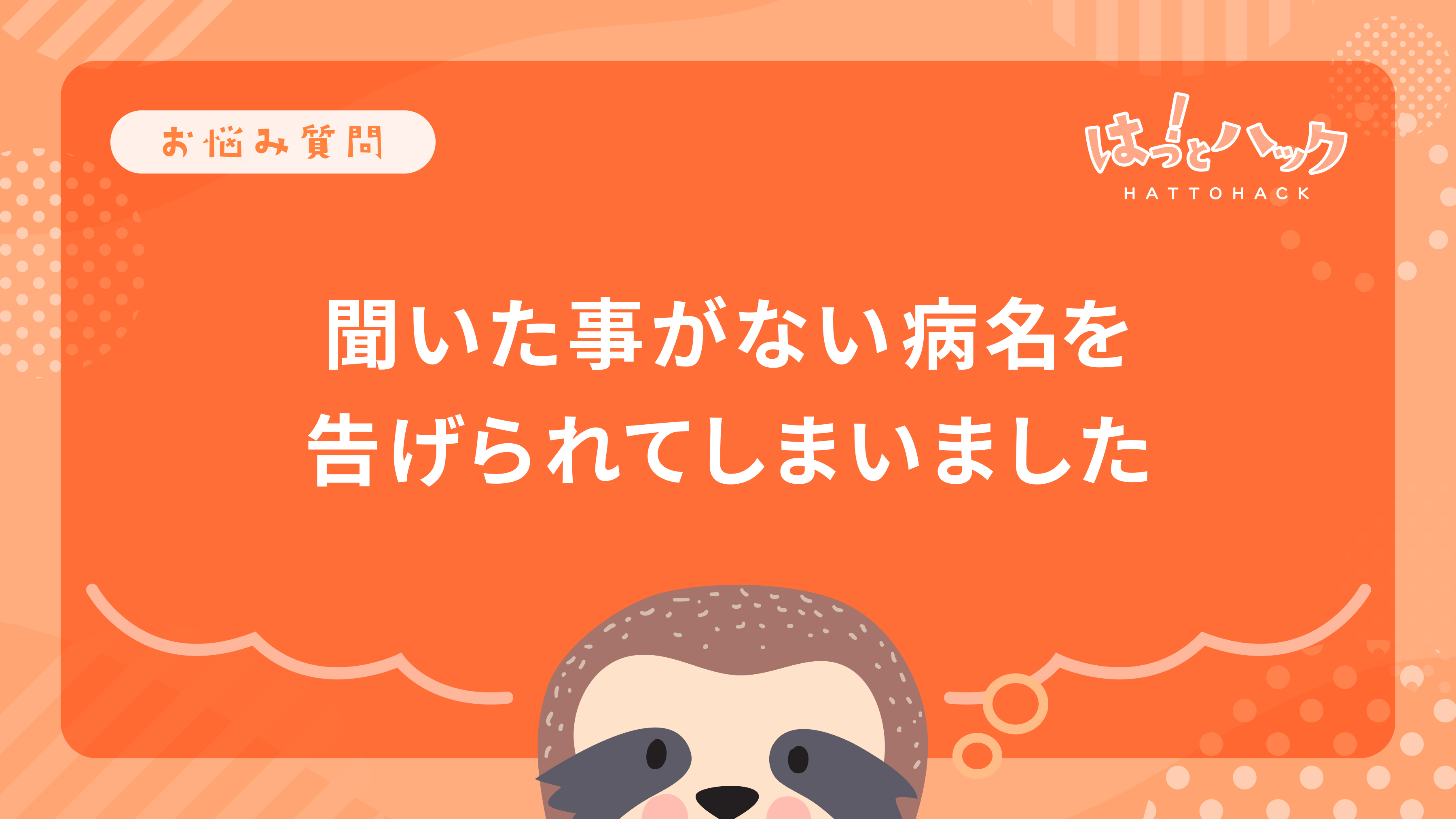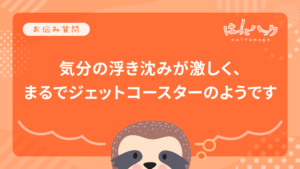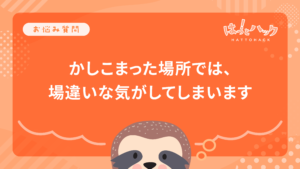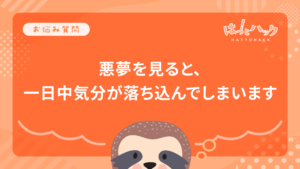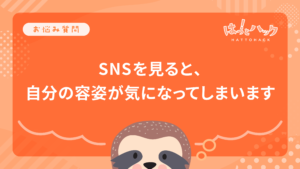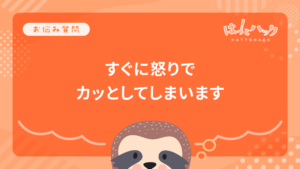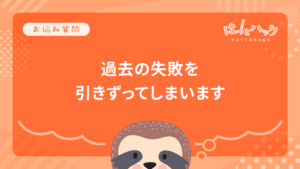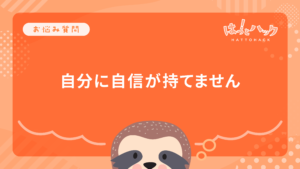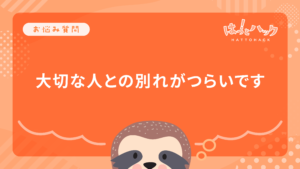はっ!とハックとは?
「はっ!とハック」とは、思わず「はっ!」と驚いてしまうような、ちょっと変わった裏ワザや解決方法のことを指す造語です。
この記事で分かること
- 未知の病名を告げられた際の初期対応
- 正しい知識を身につける方法
- 信頼できる専門家との連携方法
お悩み質問
聞いたことのない病名を告げられました。どのように受け止めたらいいですか?
聞いたことのない病名を告げられました。どのように受け止めたらいいのか分かりません。
知らない病名なので、家族や知人にどう説明すればいいのかも分からず、周囲にはまだ話していません。

一般的な解決方法
- 主治医の話をしっかり聞く
- 専門家(医療従事者)から情報を教わる
- 同行者に一緒に来てもらい、情報を共有する
はっ!とハック
病識を身につけてみてはどうでしょうか?(投稿者:Moogleさん)
※この内容は個人の経験に基づいています。正確な情報や治療については、必ず専門家にご相談ください。
聞いた事の無い病名を告げられると、どのように受け止めたらいいのか分からなくなりますよね。
私も9年前に今まで聞いた事のない病名(難病)を告げられました。
最初はやはりなかなか受け止められず、苦労しました。
今ではある程度の病識を身につけて、かなり受け止められるようになっていると思います。
これから書く内容は自分の経験ですが、少しでも質問者の方のお役に立てば幸いです。
情報収集【病識を身に付ける】
私の場合は、まず情報収集から始めました。
どういう病気で、どのような症状があるのか?どのような検査があるのか?
原因はあるのか?ないのか?どのような治療薬があるのか?薬の副作用にはどんな種類があるのか?
自分の病気に対する知識を持つことは「病識」と表現されます。
病識とは、自分の病気への認識や理解のことで、精神疾患を持っているという自覚や、治療の効果や必要性の自覚などが含まれます。病識が高い人は、自分や他人の病気に対して適切に対処できる傾向があります。
また、病識の欠如は、心の病気においては非常に一般的な状態で、自分が病気であることを認識できないことを指します。病識を持つことは、病気から回復し、発症前の生活を取り戻すための重要なステップです。
精神疾患だけでなく、難病を含む他の疾患においても病識は非常に重要です。
病識があると、患者は自分の病状を理解し、治療計画に積極的に参加することができます。
これにより、治療の遵守が向上し、病気の管理がより効果的になる可能性があります。
例えば、難病の患者は、病気を受け入れるプロセスを経ることがあります。このプロセスには、病気の告知を受けた後の心理状態の変化が含まれます。
この変化は、エリザベス・キューブラー=ロスが提唱した「死の受容過程」の5段階(※エリザベス・キューブラー=ロスが提唱した死と死期の受容)に似ており、否認、怒り、取引、抑うつ、受容の段階を経て、最終的に病気を受け入れることになります。
病識がない場合、患者は治療を拒否したり、中断したりする可能性が高くなります。そのため、医師や医療従事者にとっても、患者の病識を理解し、適切な介入を行うことが重要です。
病識を持つことは、患者が症状を管理し、病気と共に生きるための希望を持つことにもつながります。
したがって、難病であっても病識は必要です。
患者が自分の状態を理解し、治療に協力的になることで、より良い健康結果を得ることができるからです。
病識 | 看護師の用語辞典 | 看護roo!
https://www.kango-roo.com/word/5335
ドクターに質問できる知識を身につける【病識+】
ある程度の病識を得たら、次の段階へ進みます。
私の場合は、検体検査(採血)の各項目が示す内容や、異常値の場合に疑われる症状、さらにこの検査が何のために行われているのかを調べていきました。
不安な点があれば、診察時に医師に質問して解決するようにしています。
少しでも不安なことや心配なことは、医師に質問して安心感を得るようにしました。
医師に効率よく質問するためのポイントをいくつかご紹介しますね。
- 事前に質問を準備する:診察前に、聞きたいことをリストアップしておくとスムーズです。具体的な質問を用意することで、診察時間を有効に使えます。
- 具体的な質問をする:「どうしたらいいですか?」ではなく、「この症状に対してどの治療法が最適ですか?」のように、具体的な質問をすると医師も答えやすくなります。
- メモを取る:医師の説明を聞きながらメモを取ると、後で見返すことができ、理解が深まります。
- 理解を確認する:医師の説明を自分の言葉で要約して、「私の理解は正しいですか?」と確認すると、誤解を防げます。
- 他の治療法について尋ねる:提示された治療法以外に選択肢があるかどうかを尋ねると、より多くの情報を得られます。
- 指示書や参考資料を求める:必要に応じて、指示書や参考となる写真や動画などを求めると、理解が深まります。
これらのポイントを押さえて、医師とのコミュニケーションを円滑に進めてくださいね。
医師への質問のコツはたった2つ。
https://www.kango-roo.com/work/1098/
同じ病気を持つ人と繋がる方法
病識を得るようになってから、医師とのコミュニケーションが格段に円滑になった気がします。
そして、次の段階へ進みます。それは「同じ病気の人と繋がりを持つこと」です。
私は、自助グループやSNS、自分で執筆している闘病ブログを通じて、同じ病気の方と知り合うことができました。
周囲に同じ病気の人がいない場合、「孤独感」が辛くなることもありますが、同じ病気の人と繋がる方法はいくつかあります。以下の方法を参考にしてみてください:
- オンラインコミュニティやSNS
DayRoom:同じ病気の人と繋がるためのSNSです。病気ごとにトークルームがあり、経験談や病院の評判、治療に役立つ情報を共有できます。
こころシェア: 統合失調症や双極性障害などの精神疾患に特化した情報サイトで、同じ病気を持つ仲間と気持ちを分かち合うことができます。 - 当事者会
地域や病院で開催される当事者会に参加することで、同じ病気を持つ人たちと直接交流できます。悩みを共有したり、情報交換ができる良い機会です。 - サポートグループ
病院や地域の保健所で開催されるサポートグループに参加するのも良い方法です。定期的に同じ病気を持つ人たちと会い、サポートし合うことができます。 - オンラインフォーラム
病気に関するオンラインフォーラムや掲示板に参加することで、同じ病気を持つ人たちと情報交換ができます。これらのフォーラムでは、匿名で質問や相談ができるため、気軽に利用できます。
これらの方法を活用して、同じ病気を持つ仲間と繋がり、支え合いながら治療に取り組んでくださいね。
ピアサポーター
ピアサポーターとは、同じ病気や障害を持つ人たちが、お互いに支え合う活動を行う人のことです。ピアサポートは、同じような経験を持つ仲間同士が情報を共有し、精神的な支え合いを目的としています。
ピアサポーターは、自身も同じ病気や障害を経験しているため、他の人の気持ちや悩みを深く理解し、共感することができます。これにより、専門家や家族には話しづらいことも、安心して話せる環境が提供されます。
ピアサポートの活動は、個別の相談からグループでの話し合いまで、さまざまな形で行われており、地域社会やオンラインでも広がっています。
1人で抱え込まない
ここまでさまざまな方法を紹介してきましたが、いかがだったでしょうか?
1人で抱え込むのは本当に大変だと思います。私もそう感じたことがありますが、一番辛かったのは、自分だけが苦しんでいるという孤独感でした。この記事が少しでもあなたの気持ちを楽にできたのなら、嬉しいです。


この記事を書いた人
Moogle
難病とADHDの当事者であり、デザインが得意なライターです。
自身の経験をもとに、日常生活に役立つアイデアを発信しています。
記事ではイラストを取り入れ、わかりやすく伝えることを大切にしています。